物事を習得する戦略〜コツは疲労骨折と同じしくみ
疲労骨折というものがあります。
俗に言う「オーバーユーズ(使い過ぎ症候群)」というもので、スポーツ選手などが練習のしすぎでよく骨折状態に至るアレです。
ボキッ!!と折れるんじゃなく、じわじわ折れるやつです。
何かを習得するには、反復性負荷が必要
医学的に疲労骨折とは、「健康な骨に、繰り返し外力が加わった場合に生じる骨折のこと」です。
疲労骨折とは
「反復性負荷」により骨折状態という「不可逆的な状態」に至ること
この疲労骨折が起きるしくみというのが、物事の習得のコツに似ている、という話をします。
疲労骨折型上達法と名付けます。
物事を習得するのに必要なこと
物事を習得するには
「反復性負荷をかける」(=一定以上の量と頻度で練習する)
ことによって
「不可逆的な状態に至らせる」(=忘れず定着する)
必要があります。
この「反復性負荷」については条件が2つありますので次にお話しします。
反復性負荷の最低条件
1 一定期間は、負荷の間隔をあけすぎないこと
最低でも数ヶ月は毎日やらないとダメ、ということです。
間隔があくとやり方を忘れてしまいますので、毎日〜3日に1回程度は練習をしたい。(たとえばね)
なおかつ、ある程度(最低3ヶ月〜半年)はそれを「やめない」期間が必要です。
ですのでまず「間隔」と「期間」を初期設定してください。
間隔と期間が保たれていなければ「やり方をわすれる、カンが鈍る」を防げず、不可逆な地点に辿り着くことができません。
2 負荷の量は一定以上は必要
筋肉をつけるのに1日1回の腹筋じゃさすがにだめだよね、ということです。
よくある習慣化メソッドで「筋トレを習慣化したいなら1回だけやりましょう」というのがありますよね。ちょっとだけでもやればOK!というやつ。
あれは「習慣化」が目的であれば意味があるメソッドです。
しかし「結果を求める」のであれば、量が必要です。
耳がいたいです。いたすぎます。
後退することも考慮しなければならない
コツコツやればいつか辿り着く足し算のようなイメージを描きがちですが、間隔が空いたり、実施期間が短すぎたりすれば「忘れる」「カンが鈍る」「定着しない」などの逆戻り・引き算が起こります。
やはり一定期間は密な間隔で、一定以上の負荷をかける必要があるのです。
イメージしてください。部活で走り過ぎてある時から足がだんだん痛くなってきて、レントゲン撮ったら骨折!と言われびっくりしている中学生を。
骨折したくて毎日走ってないのに、結果的に「毎日負荷をかけ続けた結果、骨折を達成した」ということが起きてます。
これをポジティブに変換して、「なにかができるようになること」に応用したのが、私の提唱する「疲労骨折型上達法」でした。
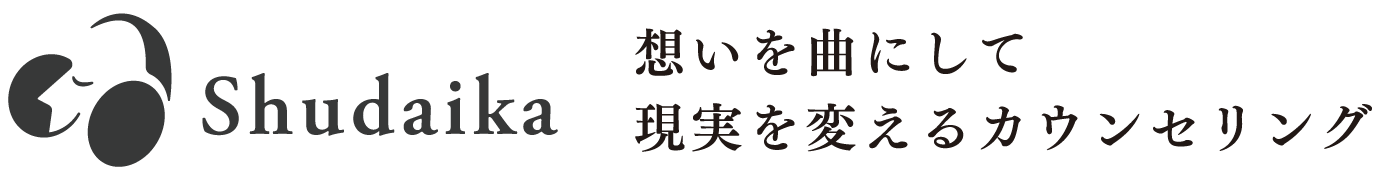
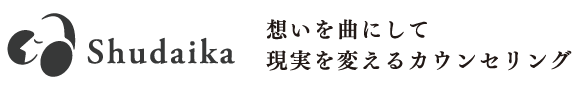
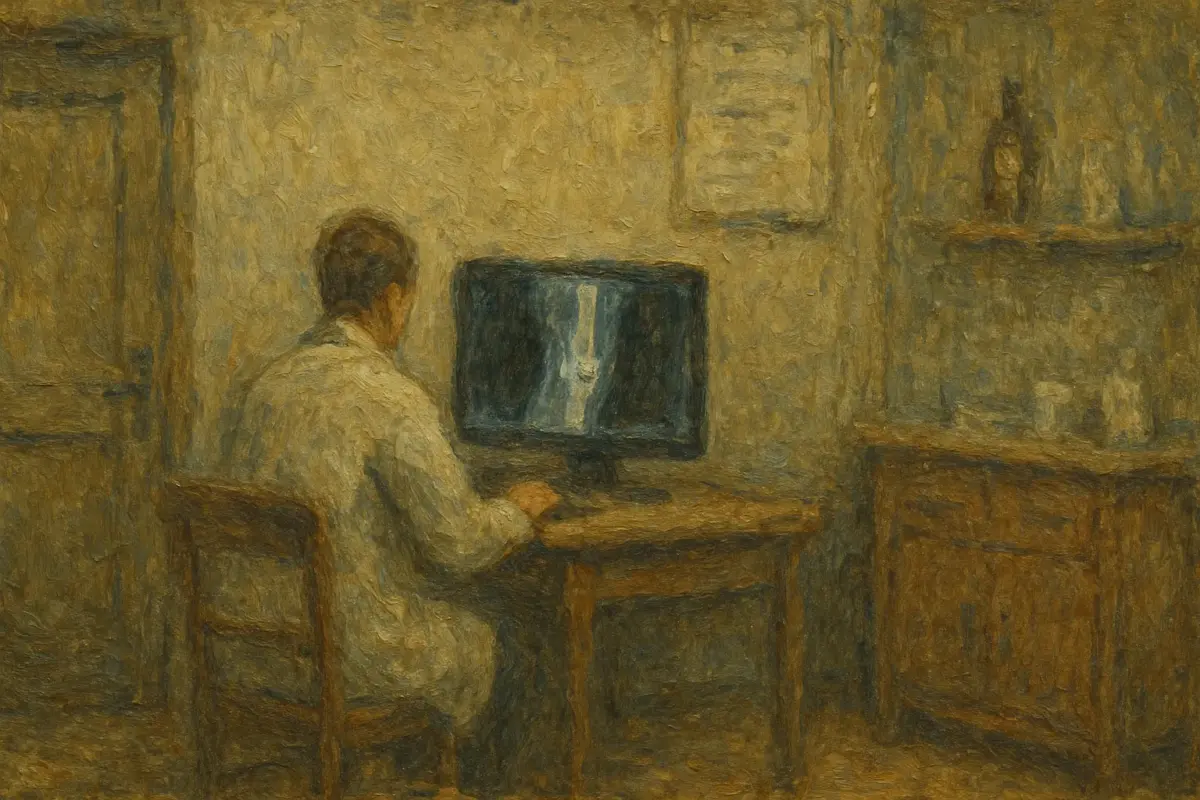
この記事へのコメントはありません。